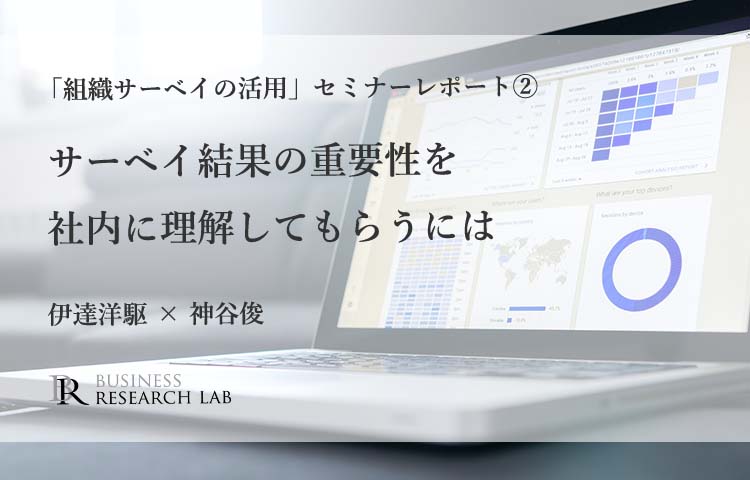2021年10月21日
サーベイ結果の重要性を社内に理解してもらうには:「組織サーベイの活用」セミナーレポート②
※本コラムは、ビジネスリサーチラボが2020年10月に開催した「組織サーベイの活用:組織サーベイをどう活かせば良いか」をもとに編集・再構成したものです。
調査結果の重要性や深刻さを伝える方法
伊達:
それでは、アンケート回収後の話に展開します。
神谷:
今、チャット欄でも「サーベイ結果の解釈を向上させるためにはどうしたらいいか」という質問が出ていますね。この点も踏まえつつ、実施後のポイントについて述べたいと思います。
サーベイ結果を社内にフィードバックする際に起こりがちなのが「伝わらない」という問題です。
フィードバックの際に重要なのは、リアルなイメージを共有できるような調査結果にしていくことです。
具体的なコメントやインタビュー内容など、現場のリアルを伝えるための質的な情報を付加していくことが重要かなと思います。いま、自社で何が発生しているのかをイメージしやすいし、問題意識も共有しやすい。
インタビューを人事が実施するのは、かなり繊細な配慮が求められますが、いまや人事担当者が現場にアプローチするのはマストな振る舞いだと思います。
丁寧に心理的安全を担保しながらインタビューやワークショップなどを実施して質的データを収集していくのが良いでしょう。自由記述式のアンケートを活用するのもありだと思います。
伊達:
「組織サーベイ」と言うとアンケートが想定されやすいと思うんですけど、インタビューもあわせて行うと、改善に向けた推進力が増しますね。
それから、そもそも、いまいただいている質問自体にも含意があると思います。「結果の解釈を向上するには」という質問をしている時点で、組織サーベイの重要な壁を一つ越えています。
というのも、結果を額面通り受け取って、施策に活かそうとする企業は多いからです。
しかし、むしろ「何故こんな結果が出たんだろう」「複数の結果を組み合わせると何が言えるんだろう」といったことを読み解くプロセスを挟むのが非常に大事です。
ただし、解釈しようとしても、「この結果はよく分からない」となるときがあるかもしれません。そのような場合、その結果をもとに施策を打つのは少し待つべきです。
経営層を説得する意味でも、サーベイ結果の妥当性を高める上でも、説明のつかない結果にもとづく拙速な判断は避けたほうが良いでしょう。
インタビューや学術研究で調査結果を補強
神谷:
まさにアクションリサーチって、そういうことですよね。現場に足を運んで、現場の言葉を聞きながらサーベイの解釈を深めていくというプロセスですね。
反対に言えば、それが必要だということは、組織サーベイ単体で組織の実態を把握するには限界があるっていうことだと思うんですよ。
やっぱり、データで見て取れる部分っていうのは、パズルのいくつかのピースは集められるけれども、完成図は見いだせないということだと思うのです。
最近のプロジェクトの事例ですが、テレワークを推進している顧客企業で、社会的孤独や抑うつ傾向に関するサーベイを行って分析を進めました。
リスクを検証していったときに、「40代後半から50代前半」「管理職」「家族あり」で、「子どもが2人以上いる」社員のリスクが非常に高いっていう結果が出たんです。40代半ばぐらいまでは統計的な有意性は見られないのに、40代後半ぐらいになってくると、途端にリスクが上がってくるんです。
これは何なんだ?って思いますよね。いくらデータを検証しても、それ以上は見えてこないんです。
アンケートの中で自由記述で書いてもらった膨大なキーワードをテキストマイニングで引っ張り出してきて、何度もデータの洗浄やまとめを繰り返しても、「通信」「子供」「ストレス」「部屋」というキーワードが浮かび上がるだけで、私の頭では点が線にならないんですよ。
サーベイ前に「40代後半」特有のリスクは想定していませんから、設計していなければ、見えない。掬い取る網がないのに、捕まえることはできないってことです。
現場に行って、該当する社員層に話を聞いて初めて合点がいきました。
「40代後半」になると、子供の年齢が比較的上がってくるんです。学校に通う年齢になり、授業や塾の勉強がオンラインになったりする。あるいは、友達とのコミュニケーションをオンラインでやったりする。そうすると、通信量を子どもが独占しちゃうんですよ。
親が「管理職」としての仕事を全うしようとすると、仕事に支障が出るか、子供に支障が出るか、どっちにしても問題は発生する。いわゆるワークファミリーコンフリクトを避けられない状況になるんです。
これは、ご本人からするとかなり辛いだろうなというのが痛々しいほど分かる。
そういうようなリアルな状況が、質的な情報を集めるほどに見えてくる。人事担当者は、それを通して自分自身の学習を進めながら、今、組織で何が起こっているのかを把握することができるわけです。
伊達:
今のような説明をされると、経営層にとっても納得がいきますよね。つまり、組織サーベイで得られるデータには限界があり、その結果を補強する素材が必要です。補強する素材の一つがインタビューですね。
もう一つ有効な素材になるのは学術研究です。ある会社の組織サーベイで、キャリア自律の支援があるほうが離職意思が下がるという結果が出たとします。これに対して、担当者も経営層も「何故こんな結果が出るんだろうか」と不思議に思うかもしれません。
これに対して研究知見なら解釈もしやすい。組織から支援を得られたと知覚すると、組織に対して愛着が高まることが分かっています。要するに互恵性が作用するわけです。
このように説明すれば説得力が増しますし、分析結果が妥当かどうかの検証も行うことができます。
さて、ここまで神谷さんと私で対談を進めてきましたが、残された時間で質疑応答を行います。チャットで頂戴している質問に順番に回答していきましょう。
各部門に分析・考察を任せるべきか
| Q. 弊社では、サーベイのツールを導入し、各部門にツールのアカウントを付与し、分析してもらうことを考えていました。しかし、ふたを開けてみると、ツールに対する理解度やスキルに差があり、同じ結果を見ても分析や解釈の内容がばらばらです。やはり、人事がまとめて分析するのが現実的なのでしょうか。 |
伊達:
部門ごとに分析を行うことについては、魅力と限界の両方があるかと思います。魅力については、自分たちの部門の問題を自分たちで発見し、自分たちで解決していこうとする当事者意識が芽生えやすい点です。
他方で限界もあります。「知識」と「関心」が低いと、適当に済ませてしまったり、目立つ箇所のみ対応したりする恐れがあります。
サーベイや分析に関する知識や関心は、まさにレディネスと言えるかもしれません。もしマネジャーに分析を任せるのであれば、事前に知識と関心を高めるような働きかけが必要です。そうした働きかけがないと、魅力を十分に享受できないと思います。
神谷:
伊達さんの話につけ加えるのであれば、メリットとして「スピード感」はあります。現場のアカウントを持てば、毎日とか週次でデータを取って、現場の実践にダイレクトに反映することはできるでしょう。スピード感を持った改善活動はしやすいです。
一方で、伊達さんが言ったように、専門知が不足していることで、データをひも解きながら問題のメカニズムを推察することを求めるのは難しいのかなと思います。
組織開発もアクションリサーチもそうですが、全てのアプローチが組織というものを紐解くための学習プロセスなんですよね。
理論的・経験的な専門知識を踏まえながら少しずつノウハウが蓄積されていくという側面も多分にある。日常的に別業務に従事している現場社員が、果たしてそのレベルを即座に修得できるかというと、難しいところはあるんじゃないかなとは思います。
伊達:
そうした学習コストを負担できないと、知識のない中で分析・解釈し、対策を打つことになります。そこで発生し得るのが確証バイアスです。自分の信じている情報を選んでしまう状態です。
例えば、「うちの部署はこういうふうになっているはずだ」と考えていると、その信念に関連する結果が浮き上がって見えます。そして、「ほら、やっぱりそうなっていた」と信念が強化されるわけです。
神谷:
もしやるならば、もう切り分けちゃって、スナップショット的にスピード感を持って現場を把握するみたいなアカウントは、現場で持っていていい。
ただ「大きな絵」をマクロな視座で描いたり、それを成すために戦略を立てていくというような目的があるならば、別の観点でサーベイを設計する方がいい。現場のメカニズムとか組織のメカニズムをつくっていく感じで、切り分けてやっていくといいかなと。
伊達:
例えば、質問項目を切り分けるのもありだと思います。現場で活用する場合には、具体的な質問にしておく。そうすれば、改善策も取りやすくなります。
回答者へのアナウンスをどうするか
| Q. サーベイ実施時、対象者へのコミュニケーションで注意すべきことはありますか。 |
神谷:
アナウンスするときにどうするかっていうことですよね。ここは、収集データの運用方法の詳細・目的についてしっかり伝えるのがマストです。
「匿名性を担保します」「人事評価には全く影響しません」とか、そういうお決まりの内容はもちろんのこと、「経営層としてこういう事業計画や組織展開を考えていて、こういうポイントについてデータを収集しています」「収集したデータを踏まえ、こんな対策を採っていきたいと考えているので、アンケートにご協力ください」という感じですね。あとは、回答に必要な所要時間や回答可能なデバイスも記述したりします。
他社比較に意味はあるのか
| Q. サーベイ結果の良い・悪いはどう判断すればいいでしょうか。 |
神谷:
自社のサーベイ結果について、何をもって「良い・悪い」と判断するのかという質問ですね。非常に大事な観点です。
他社との比較をして、ランクづけや点数化をして「良い・悪い」を定義づけるケースをよく耳にします。しかし、これは、個人的にはあまりお薦めはできません。
他社と自社は前提が大きく違います。事業内容、設立年数、現在の業績、将来的な業績目標、平均年齢や給与レベル等々、サーベイ結果に作用する「変数」が無数にあるわけです。
そのような前提の違いがあるにもかかわらず、自分の会社のほうがある特定の項目が1pt低かったとしても、それはどういう点で問題だと言えるのかは正直分からないと思うんです。
良い悪いっていうのは、自社内のデータと向き合いながら定義付けていくのが妥当でしょう。例えば、経年での離職率、労働分配率、人事評価平均、昇進昇格ピッチ、配置転換、売上、利益率など、色々なデータがありますよね。そういう自社内の数値と関連させながら、データ結果を分析していくのが妥当かなとは思います。
あと、「良し・悪し」が最も分かりやすいのは、質的調査のデータですよね。インタビューで、明らかに現場が憤りや怒りを感じているとか、それを通り越して諦めのような感じになっているとか。
そこで、データ結果を見てもエンゲージメントが明らかに低いというのであれば、それはもう「悪い」と言ってよいと思います。
伊達:
組織サーベイを実施する際、よく聞かれるのが「他社との比較はできますか」というものです。経営層に深刻さをアピールする材料にはなるかもしれません。経営層への説得が主たる目的となる組織サーベイであれば、他社比較を入れても良いかもしれません。
しかし実際のところ、神谷さんの言う通り、測定的にも分析的にもあまり意味のある比較ができないケースがほとんどです。基本的にはおすすめはしません。
それより「社内」で比較をした方が有効です。部門や属性などで比較するということです。社内であれば文脈が分かります。「この部門が何故低いのか」を解釈しやすい。
データがあれば課題は見えるか
| Q. 組織サーベイではなくBIツールで、労働時間、売り上げを可視化したのですが、そこから課題を分析して施策を立てるというのは難しいんでしょうか。 |
神谷:
これは、いま申し上げた「他社と比較しても、影響する変数が多すぎてお薦めしない」という話と関連するところかなと思います。
稼働時間や売り上げで生産性のようなものを算出はできます。しかし、この「売り上げ」が、外部環境や扱っているサービス特性などの影響をかなり受けるので、その結果だけで問題を定義づけたり、対策を考えると、視野が限られてしまうリスクがあります。だから、稼働時間や売り上げだけではなく、別で採った組織サーベイの結果が必要になるのでしょうね。
組織に対する愛着や育成環境、管理職に対する評価等、複数の視点を関連させて見ていくと、立体的な視野が見いだせてくると思います。
伊達:
Garbage in Garbage outという格言があります。簡単に言えば、良いデータを入れないと、良い結果が出てこないということです。
良いデータを得るために必要なのは、仮説をきちんと立てることです。例えば学術研究やインタビュー・実践知などに基づいて仮説を立て、その精度について吟味した上で、集めるべきデータを考えます。
BIツールを導入する企業から、「いろいろ分析しているが、あまり結果が出てこない」といった相談を受けることもあります。話をよく聞いてみると、仮説が十分に練られてないんですよね。
組織文化をいかに測定するか
| Q. 目指すべき組織文化があって、そのためにサーベイを実施しようと思っています。そのときに気を付けることはありますでしょうか。 |
神谷:
最近、文化を重視する企業は増えていると思います。マネジメント機能を弛めて、自立性を促し、文化で方向づけをするという組織戦略ですね。ビジョン、ミッション、バリューとか、カルチャーを重視する企業は多いです。
組織文化っていうのは、やっぱりサーベイはしにくいと思います。経営学でも、その企業の組織文化そのものを定量的に測定するのは難しい…っていう考え方もありますので。
組織文化そのものではなく、「どういう人材を増やしていきたいのか」「その人材に求めるアクションはどういうものか」「求める仕事観はどういうものか」というところまで解像度を高めて測定しても良いかもしれません。
伊達:
組織文化の深層については神谷さんの言う通り、組織サーベイでは測定が困難です。一方で、人が知覚できる表層であれば、定量的な測定も可能で、学術界でも組織文化を測定する尺度もあります。
そのことを踏まえた上で、大事になってくるのは、組織文化を測定することに併せて、そのような文化を醸成するための要因も一緒に測定していく必要があるという点です。先ほどの私の言葉で言えば、前者が成果指標、後者が影響指標ですね。
特に影響指標を測定しなければ、打ち手が分からないままに終わります。それでは、何のために組織サーベイを実行したのか分からなくなってしまいますよね。
利害関係者の意識合わせをどうするか
| Q. 組織サーベイ結果の意思決定に関わるステークホルダーで、問題意識が共有できていません。ステークホルダーの問題意識をどうやって共有したらいいでしょうか。 |
神谷:
経営層も、事業部長も、部長クラスも、みんな考えていることが違うので、そこがいきなり一致するのは難しいですね。ここの部分を巻き込みながら推進していくのが、組織開発になっていくと思います。さっきの伊達さんのベターメントの話にも関連しますね。何をもって「良い・悪い」とするのかを、コミュニケーションを交わしながらまとめ上げていくことが必要です。
ただ、コミュニケーションだけでまとめ上げられたら、もうその人はコンサルタントに転職したほうがいいレベルのファシリテーション能力です。いきなりまとめることはやはり難しい。予備調査や事前調査が必要になってくると思います。
事前に現場にヒアリングして情報を集めたり、事前にデータ武装した上で、全体の共有認識をつくり上げていく。現状確認をしたうえで、ステークホルダーのコメントや意見を引き出し、調整していくというアプローチが求められます。
伊達:
組織サーベイの結果をいきなり持っていって議論するのは避けたいところです。設計段階で、各自の想定するベターメントをしっかり可視化しておいた方が良いですね。そうでなければ、後出しじゃんけんの応酬になり、収集がつかなくなってしまいます。
といったところで、駆け足ではあったんですが、全ての質問に答えることができました。
以上で、本日の対談を終了したいと思います。ありがとうございました。
(了)
登壇者
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。近著に『オンライン採用 新時代と自社にフィットした人材の求め方』(日本能率協会マネジメントセンター)や『人材マネジメント用語図鑑』(共著;ソシム)など。
法政大学大学院経営学研究科 修士課程修了。修士(経営学)。2016年9月に株式会社エスノグラファーを創業し、人事・組織領域やマーケティング領域において、エスノグラフィーを中心に据えた複眼的なリサーチ&コンサルティングサービスを展開している。2020年4月に新たにVirtual Workplace Lab.を発足。リモートワークに従事する従業員のリスク抽出や、バーチャルワークプレイスを展開する企業の組織課題抽出に特化したサービスを展開している。